

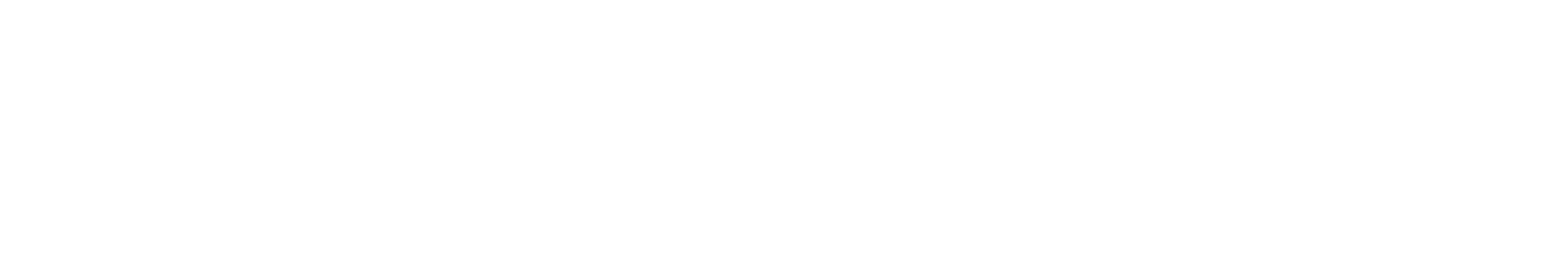
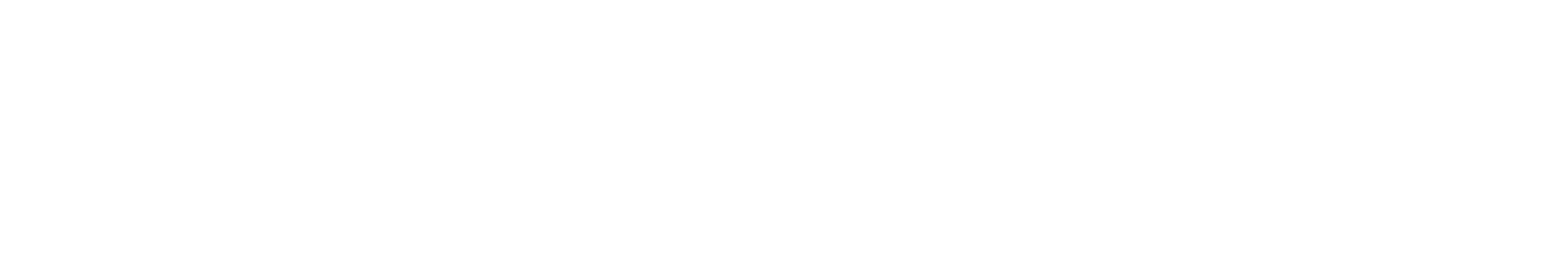
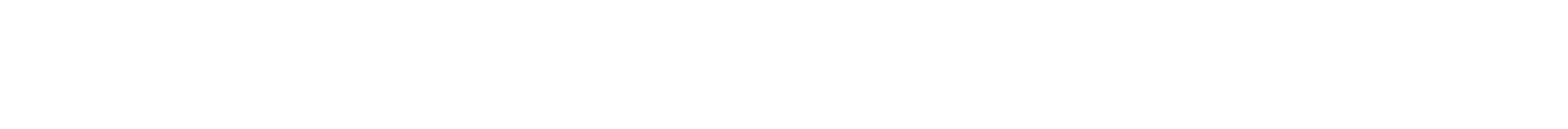
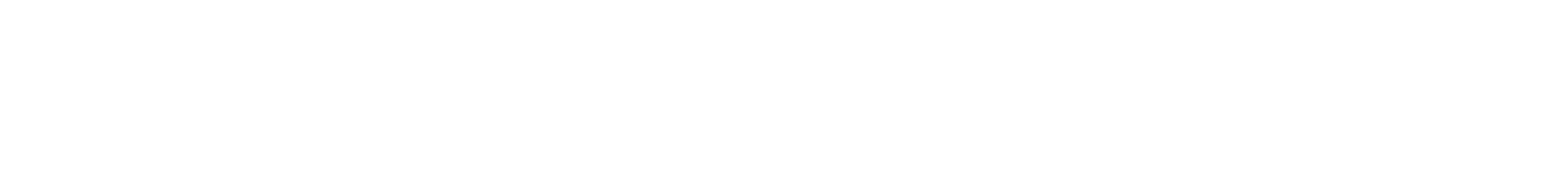
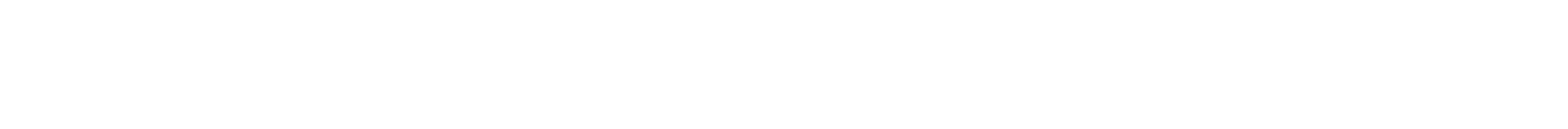

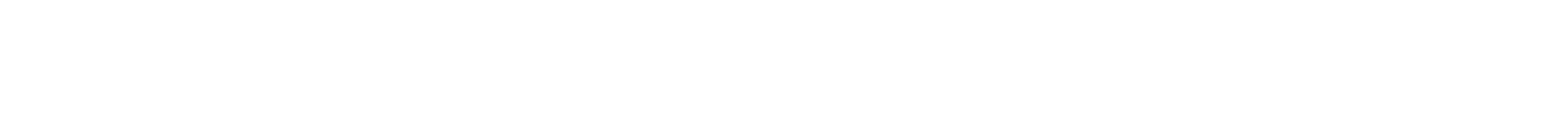
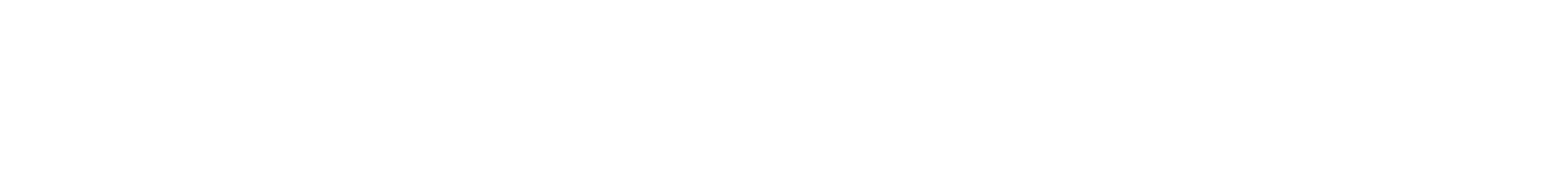

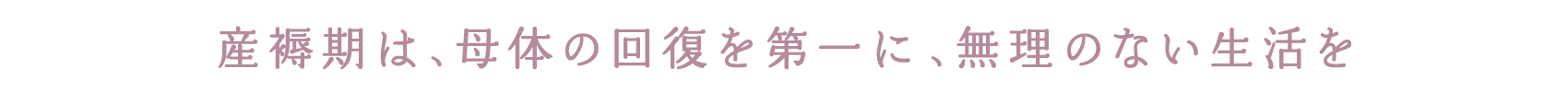
出産後の母親は、出産により子宮が傷を負った状態にあり、体力も消耗しています。
この状態から妊娠前の身体に戻る時期(出産後約6~8週間)を「産褥期」といい、傷ついた子宮や
消耗した体力を回復させるために、横になって身体を休める必要があります。
続きを読む
産褥期の身体が回復しないうちに、赤ちゃんや上の子のお世話、家事をするなどして無理をしてしまうと、
出産の疲れも癒えることのないまま、新たな生活に突入してしまいます。
母親の心身の負担が増すばかりでなく、段々と産後うつになってしまうことも。
産後ドゥーラは、母体の回復を第一に考え、母親が安心して休んでいられるよう、
母親の代わりとなって育児や家事をサポートします。
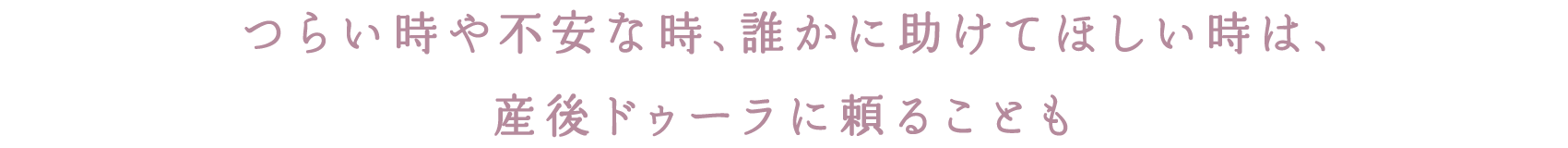
妊娠中から産後は、母親の心身や生活が大きく変化する時期です。
睡眠不足や疲れ、自分の身体や育児への不安、思うように家事のできない生活など、一人ではどう
することも出来ない状況になることもあります。
続きを読む
何かやって欲しいことが明確なわけではなく、とにかく今のつらい状況を何とかしたい、
ということもあるでしょう。産後ドゥーラは、その時々の母親の気持ちに寄り添いながら、
その時の状況に合わせたサポートを行います。
頼ることができること、頼れる人が身近にいることは大切です。
産後ドゥーラは、優しさを持って受けとめ、
頼られる存在として産後の母親を見守り支えます。

産後は、母親となる育児人生の大事なスタート地点でもあります。
初めての出産だけでなく、2度目3度目でもそれぞれに状況が異なり、いつもが新たなスタートです。
続きを読む
自分のやり方でよいのだろうか、上手くいかないのは自分のせい?
母親の中には、自問自答を繰り返し自信を失くしてしまうこともあります。
これから長く続く育児人生のスタートは、良いイメージで通過してほしい。
産後ドゥーラの「大丈夫」の一言が母親達を強くします。
赤ちゃんが生まれた喜びがいつまでも続くように、
産後ドゥーラは母となりゆく女性を応援します。


